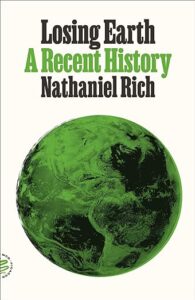人新世の「資本論」
斎藤幸平. 2020、集英社新書
2020年に刊行され、この種の本にしてはかなり話題になった。斎藤氏(当時は大阪市立大、現在は東大)はマルクス研究者だし、タイトルもマルクスの「資本論」の新解釈と思わせるので、実はサステナ関係者にはスルーしていた人もいるかもしれない。実際には、サステナビリティ推進に取り組んでいれば誰もが感じたことがあるはずのジレンマ「気候変動対策は経済成長と(或いは「豊かさ」と)両立するのか?」というテーマについて掘り下げた著作だ。
資本主義とは、価値増殖と資本蓄積のために、さらなる市場を絶えず開拓していくシステムである。そして、その過程では、環境への負荷を外部に転嫁しながら、自然と人間からの収奪を行ってきた。この過程はマルクスが言うように「際限のない」運動である。利潤を増やすために経済成長を決して止めることがないのが、資本主義の本質なのだ。
その際、資本主義は手段を選ばない。気候変動などの環境危機が深刻化することさえも、資本主義にとっては利潤獲得のチャンスになる。
よく世間でスウェーデンなどは近年デカップリング(CO2排出量の削減とGDP成長の両立)を達成できていると言われるが、これについても断罪される。
先進国での「見かけ上の」デカップリングは、負の部分(この場合は、経済活動に伴う二酸化炭素排出)をどこか外部に転嫁することに負っている。OECD加盟国のデカップリングは技術革新だけによるものではなく、この三〇年間で、国内で消費する製品や食料の生産を、グローバル・サウスに転嫁したことの結果なのだ。
環境学者トーマス・ヴィートマンが国際貿易を加味して実際の天然資源消費量を可視化したマテリアル・フットプリントで見れば、EU諸国も日本も、国内物質消費量は減少トレンドにあるが、マテリアル・フットプリントはGDPと同じように増えており、デカップリングは生じていない。
そしてまず序盤で
私たち自身が、当事者として、帝国的生活様式を抜本的に変えていかなければ、気候危機に立ち向かうことなど不可能なのである。
と提起される。
さて、ではどうするべきなのか、というところでマルクスが晩年に取り組み、しかし未完に終わった「資本論」第二巻、第三巻の解釈が展開される。晩年のマルクスは自然科学の研究に没頭し、エコロジカルな観点で資本主義批判をしていたというが、それが著作には残されておらず、このたび書簡や手控えのメモなども全部発掘していくプロジェクトが動き出したおかげで、そういった晩年の変化が理解され始めたのだそうだ。
鍵となる概念は「コモン」(社会的に共有され、管理されるべき富)、そして「脱成長」だ。
「足るを知る」というのはまったく新しい概念ではないし、昔から日本人が得意とするところのはずだが、私たちの多くはまだ戦後~1990年代ぐらいまでの、人口が増え続けて経済も成長し続けるのが当たり前、という価値観のままに生きている。その時代を知らない「Z世代」が、その上の世代から殊更に異質視されるのは、この根本的な価値観のズレのせいだろう。
別に脱成長しなくても、経済成長を続け、新しい画期的なテクノロジーをどんどん生み出していく中で、気候変動についても解決できてしまう、という甘いシナリオを、多くの人が描いている。しかしこれもあっさり否定される。
エコ近代主義のジオエンジニアリングやNETとうった一見すると華々しく見える技術が約束するのは、私たちが今まで通り化石燃料を燃やし続ける未来である。(中略)この危機を前にして、まったく別のライフスタイルを生み出し、脱炭素社会を作り出す可能性を、技術は抑制し、排除してしまうのだ。
本来、危機はこれまでの振る舞いに自制をうながし、違った未来を描くきっかけとなるはずなのだ。ところが、そのために不可欠な想像力・構想力が、専門家が独占する技術によってはく奪されてしまうのである。実際、気候変動についても、きっと技術が問題を解決してくれる、と思っている人は多いのではないだろうか。
「脱成長」というワーディングはちょっとやっかいで、ちゃんと本書を読まないで言葉のイメージだけで捉えてしまうと、「江戸時代の暮らしに戻るのか」とか「シェアリングエコノミーのことか?」と思ってしまいがちだが、その点も釘が刺される。
旧来の脱成長派は、消費の次元での「自発的抑制」に焦点を当てがちである。節水・節電をして、肉食をやめ、中古品を買い、モノをシェアするという風に。ところが、所有や再分配、価値観の変化だけに注目し、労働の在り方を抜本的に変えようとしないなら、資本主義には立ち向かえない。
これを踏まえ、①使用価値経済への転換、②労働時間の短縮、③画一的分業の廃止、④生産過程の民主化、⑤エッセンシャル・ワークの重視 が柱として掲げられる。それぞれの中身に触れ始めると長くなりすぎるので割愛する。
資本主義から脱成長コミュニズムに転換すべし、と言われても、私たちの多くはそこで思考停止してしまうだろう。参考にすべき事例としてバルセロナ市の取り組みが紹介されてはいるが、日本は目指すべき「参加型社会」から逆の方向にどんどん進んでしまっていると思う。
こういう、社会の大変革みたいなことは、やっぱりビジネス界の人からはなかなか言い出せなくて、学者さんならではの提言だと思う。ただ、これを「できるわけないだろ」と切り捨ててしまうようでは、人類に進歩はない。ここで述べられていることに同意したら、どうすればそれが実現できるのかを考えるのが、社会に生きる我々の責務だ。
もちろん斎藤氏も批判を覚悟している(主にマルクス研究者からの「批判」かもしれないけど)。そして最後に、有名な「3.5%の人が本気で動けば社会が大きく変わる」というハーバード大学の研究に触れる。日本の労働人口は7,400万人、その3.5%である260万人が本気で意識を変革することは、可能だろうか。
(2024/5/26記)